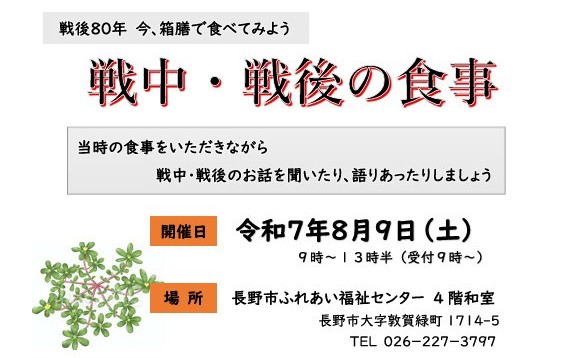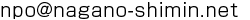戦後80年目の節目を間近に控えた8月9日、当時の食事をいただきながら、戦中・戦後のお話しを聞いたり、語り合ったりした会が信州ひらがな料理普及隊の主催で、子ども3人を含む16人が参加し開催されました。同団体は、現在カタカナで表現される料理(パスタ・ハンバーグ・グラタン等)が食卓に並ぶことが多いが、日本は、ひらがなで表現される料理が文化であるとし、その日本の文化を伝える活動をしています。

団体の会長、小学校1年生で敗戦を体験した池田玲子さんがまず自身の体験を語ります。「ひもじいって知ってるかい?腹減ったのとはわけが違う。毎日がひもじかった。お昼で持参した弁当を食べる時、弁当をもってこれない子らは、校庭の桜の木の下で絵を描いて過ごしていた。また、体育の時間で教室が留守になると、弁当泥棒があった。でも、盗るのも盗られるのも両方とも辛かった」などと語ります。


その後、事務局の吉田喜美夫さんから、「令和のコメ騒動」について統計データを交えながら解説。「一昨年の秋から米の生産量、等級割合に異変を感じていた。今後、米不足はおきないが、国産米不足は起きる」また「今後、どういう社会で暮らしていきたいか。本来の食べることの意味を見失っている?日本の景色、守ってください。未来へ繋げて欲しい」と語ります。 その後2グループに分かれ、それぞれ感想をシェア。大学生は「池田先生の話は衝撃だった」や自由研究として参加した小学5年生は「戦争中は食べ物がないこと、かわいそう」などと話していました。

そして、箱膳に並んだ、かぼちゃごはん、じゃがいもと小麦粉で作ったすいとん、いなごやどきょ(蚕のさなぎ)の佃煮、さつまいものツル、スベリヒュのお浸し、きゅうりの塩もみを食しました。
最後に「食べることは相手の命をもらうこと。ありがとう。食材とどう対話ができるかがとても大切で、かぼちゃと話しができない人はかぼちゃを食べちゃだめ」と結びました。
#情報 #NPO #長野市 #市民活動 #信州ひらがな料理普及隊 #戦中戦後の食事